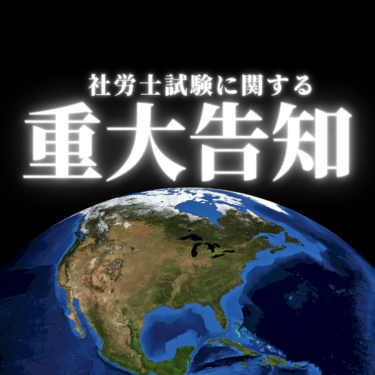独学で社労士試験合格を目指す方に向けて、実質7か月の勉強期間で独学合格した私の勉強法をご参考までにお伝えできればと思います。
今回は「どこで勉強するのが一番いいの?」について。勉強法ではありませんが、勉強環境を整えるのも大切だと思います。
結局は自宅が一番
どこで資格の勉強をするかって考えた時に思いつくのは、自宅、図書館、カフェ、コワーキングスペースなど。(独学合格を念頭に置いているので、予備校の自習室ってのは今回選択肢から除外してます)
私も図書館やコワーキングスペースなどで勉強したこともありますが、社労士の独学合格には自宅勉強が一番だと思っています。
なぜ自宅勉強が一番か、その理由を以下で述べていきたいと思います。
横断学習が必須な社労士試験
社労士試験の勉強を進めていくと、異なる科目で「同じ論点」や「ほぼ同じだけど少しだけ違う論点」がいくつも出てきます。
本当にいくつもありますが、例えば以下の項目
- 労働保険の不服申し立ては、審査請求日から3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がない時は労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 社会保険の不服申し立ては、審査請求日から2カ月を経過しても審査請求についての決定がない時は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
ほとんど同じだけど、なぜか微妙に数字が違う。。。こんなのばかりです。
勉強を進めていくと、「あれ?同じような話があっちの科目でも出てこなかったっけ?でも数字が少しだけ違う気がするし・・・気のせいかな?」「この健康保険法の適用除外とその例外の表、、、どっかで見た気がする。。。労基法の解雇予告の適用除外の表だったっけ?」のような場面に本当に何度も出くわすことになります。
この時にすぐに思い出せなかったり曖昧な記憶だったりすると、そのことばかり気になってしまい勉強に手がつかなくなりました。
逆に、気になったときにすぐにテキストや過去問で確認したことは、すごく記憶に定着につながりました。
試験範囲を一通り学習し終えたあとは、科目横断で整理し理解していくことが記憶の定着にはとても効率的かつ効果的で、独学合格には必須です。
テキストと問題集分厚すぎる問題
社労士試験の独学合格には科目横断で整理・理解していくことが必須ですが、そのためには、気になったときにすぐ他の科目のテキストや問題集を確認できる環境が必要です。
常に全ての科目のテキストや問題集を持ち歩くならどこで勉強しても問題ありませんが、社労士試験のテキストや問題集は数が多く分厚すぎて、常に持ち歩くには重すぎます。
なので手持ちの全てのテキストや問題集がすぐ確認できる自宅で勉強することが、社労士試験の独学合格には一番だと考えています。
横断整理テキストは使える?
自宅以外で勉強するときには、市販の横断整理のテキストを持ち歩けばいいのでは?とも思いますが、私は市販の横断整理のテキストは正直必要ないかなと思っています。
横断整理のテキストを買いはしましたが、何度も繰り返し見たのは「支給制限」(労働保険や社会保険の保険給付について、行わない、全部または一部を行わないことができる、支給停止、差し止める等)のページくらいで、他の項目はほとんど参照しませんでした。
といのも横断整理のテキストに掲載されている項目は、どれも重要な論点で、横断整理のテキストで整理されるまでもなく覚えなければならないし、覚えていることばかりだったからです。
それよりも「労基法の解雇予告の適用除外と健康保険の適用除外は対象が似ている。雇用保険の適用除外の対象とも似ているようで少し違う」とか「障害基礎年金の加給の対象は子、障害厚生年金の加給の対象は配偶者。これを逆にした問題が過去問頻出」とか、そういう痒いところに手が届くような横断整理のテキストが欲しかったのですが、書店で立ち読みしてチェックする限り、そういうテキストはありませんでした。
社労士試験の勉強を進めていくと、必ず「あれ、これと似たような表を見たことがある」とか「どこかで似たような問題を解いたぞ」ということに出くわします。
その時に「ま、いっか」と放置せず、すぐに確認すること、すぐ確認することが可能な環境で勉強をすることが独学合格へつながると思いますので、よろしくお願いします。